トランプ米大統領が推進している新しい税制・歳出法案「1つの大きくて美しい法案」には、「Section 899」という新たな条項が含まれている。これは通称「報復税」と呼ばれ、国際的に大きな話題となっている。これは米国による新たな資本課税である。具体的には、財務省が、①米国が不公正と見なす税制を採用している国を特定し、②これらの特定された国の政府や法人、個人などが米国での事業や米国への投資から得る利益や配当金、利息などに追加の所得税を源泉徴収するというものである。当初の税率は5%で、不当な税制が是正されない場合には税率が毎年5%引き上げられ、最大20%課されることが計画されている。
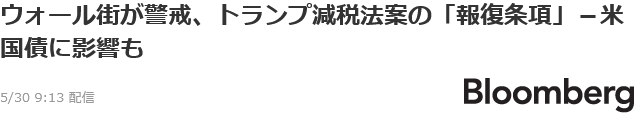
この報復税という言葉を聞くと、外国の企業や投資家に対して攻撃的な印象を持つかもしれない。確かに表面的には、米国以外の国の投資家が米国の資産に投資する際に、追加の負担が発生する可能性があるため、外国人投資家の信頼をさらに損ない、米国資産への投資意欲をそぐことになると多くの投資家が疑念を抱いている。しかし、この報復税が実際に狙っている目的は、必ずしも外国人投資家に不利益を与えることではない。
まず、この報復税が導入された背景を理解するためには、各国が導入している「デジタルサービス税(DST)」と呼ばれる税制や、「グローバル最低税率(UTPR)」という国際的な税の仕組みについて知る必要がある。
「デジタルサービス税(DST)」とは、GoogleやAmazon、Facebookといった主に米国の巨大テクノロジー企業が、世界各国で利益を上げているにもかかわらず、適切な税金を支払っていないという批判から生まれた新しい税制である。特にヨーロッパ諸国が積極的に導入している。この税制は、サービスを提供する企業が、そのサービスを利用する国で適切な税金を納めるよう強制するもので、結果的にアメリカの大企業に大きな負担を強いることになった。
また、「グローバル最低税率(UTPR)」は、企業が税率の低い国や地域に利益を移転させて税金の負担を逃れる「タックスヘイブン」を防ぐため、世界共通の最低税率を定める制度である。これも主に多国籍企業が狙われており、米国企業への影響は特に大きい。
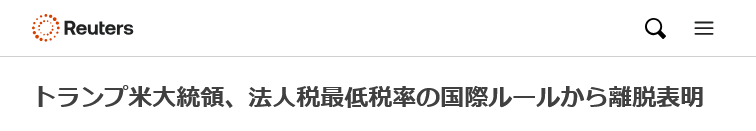
トランプ大統領の新しい報復税は、こうした税制に対抗するための手段として位置付けられている。具体的には、米国がこれらの税制を「不公正だ」と判断した場合、その国の投資家に対して追加的な税金を課すことを示唆している。しかし、実際にこの税金を徴収したいのではなく、「交渉カード」として活用することが真の狙いである。
つまり、米国政府が「あなたの国の税制は不公平だから、私たちは報復税を課す可能性がある」と表明することで、他国に対して圧力をかけているのだ。この圧力により、デジタルサービス税やグローバル最低税率といった税制を各国が見直し、撤廃または軽減する方向に動けば、米国企業は結果的に有利になる。
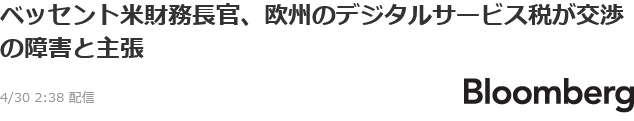
これは「貿易戦争」の戦略に似ている。関税や報復措置をチラつかせることで相手国を交渉のテーブルにつかせ、有利な条件を引き出すという方法だ。報復税の威力は、実際に発動することよりも、相手国がこの威力を恐れて税制の変更に踏み切ることにある。
一方で、この戦略にはリスクもある。もし米国が報復税を本当に導入すると、外国人投資家が米国資産を敬遠することにつながり、アメリカの資産市場に対する国際的な信頼が損なわれる可能性がある。特に、米国は世界中から資金が集まる重要な金融市場を抱えているため、投資が減ることは米国経済に大きな打撃を与えかねない。(しかし、資本課税によって国際的な資本移動を制限することは、ゆくゆくは金融システムの安定化につながる可能性があるため、デメリットだけではない)
トランプ政権はこのリスクを承知の上で、「実際に報復税を発動する前に相手が妥協するだろう」と考えているのだろう。これは、いわゆる「チキンレース」のようなものであり、どちらが先に譲歩するかの心理的な駆け引きを狙っているのである。
実際に報復税が発動されなければ、短期的には市場に混乱が生じるかもしれないが、最終的に各国が税制の見直しを行えば、米国企業は利益を取り戻し、投資家たちの懸念も解消される可能性が高い。トランプ大統領の最終的な狙いは、米国企業の競争力を高めることであり、この報復税という政策を通じて、アメリカ中心の税制へと国際社会を誘導しようとしているといえる。
結局のところ、この「報復税」の本質は税収を増やすことではない。これはあくまでも交渉材料であり、世界各国が公平でないとアメリカが感じる税制を撤廃させるための圧力なのだ。米国が望む通りに他国が動けば、米国企業は国際市場でより自由に活動でき、最終的に「勝者」として笑うことになるだろう。これがトランプ政権の狙いの核心である。

