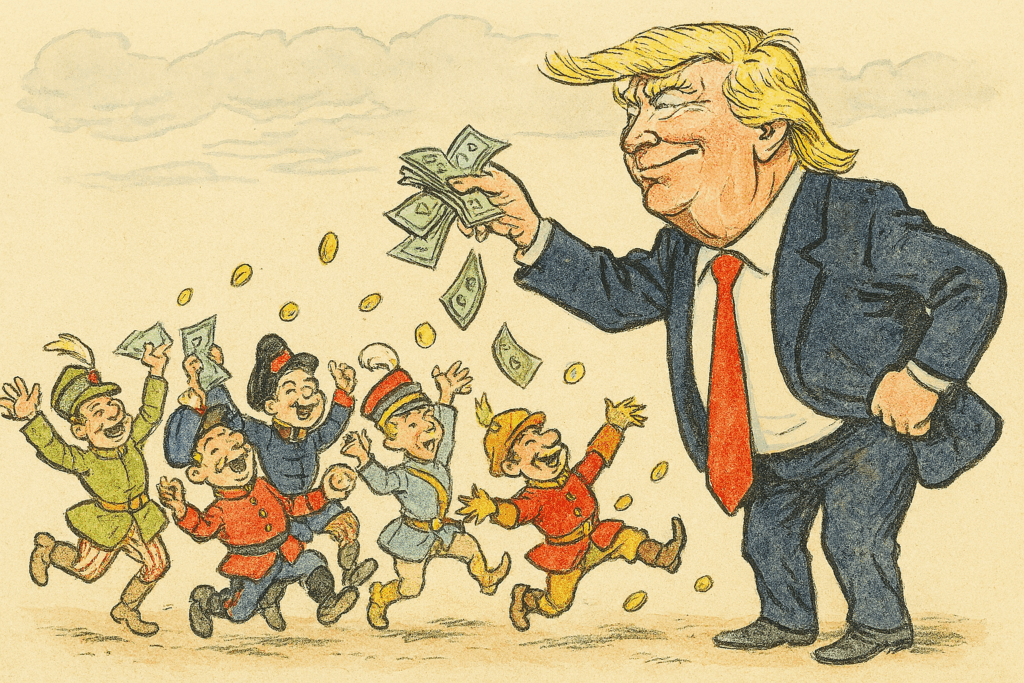
米国の小型株投資家は、トランプ大統領が掲げた『ひとつの大きくて美しい法案(One Big Beautiful Bill)』を、他のどの投資家よりも強く歓迎することになるだろう。というのも、この新たなトランプ減税では、企業の資金調達と税金計算に密接に関わる「利子費用の税控除ルール」が見直されるからである。
利子費用の税控除とは:企業は通常、事業拡大や設備投資のために銀行などから資金を借り入れる。その借入金に対しては当然ながら利子を支払わなければならない。米国税制では、この利子支払いの一部または全部を経費として認め、課税所得から差し引くことができる。これが「利子費用の控除」と呼ばれる制度である。
この仕組みは、特に米国のように企業が積極的にレバレッジ(借金)を活用する環境下では非常に重要だ。日本では財務健全性が重視される傾向にあるが、米国ではむしろ成長のために資金を借り入れることは合理的な経営判断とされる。そのため、借入にかかるコスト(利子)をどの程度まで税務上差し引けるかは、企業価値を左右する大きな要因となる。
ルール変更:旧制度では、企業が支払う利子費用のうち、税務上の控除対象となるのは「EBIT(利払前・税引前利益)」の30%までとされていた。しかしこの基準では、特に設備投資の多い企業にとって控除可能な範囲が限定的となり、税負担が大きくなるという問題があった。
新しいトランプ減税法では、この基準が「EBIT」から「EBITDA(償却前利益)」へと変更された。EBITDAとは、EBITに減価償却費(Depreciation & Amortization)を加えたものである。EBITDAは通常、EBITよりも金額が大きくなる。
控除率自体はこれまで通り「利益の30%まで」と変わらないが、基準となる利益の定義が変わったことで、実質的には控除できる利子費用の上限が大幅に緩和されたことになる。つまり企業は、より多くの利子費用を税金の対象から差し引けるようになった。
では、なぜ米国の小型株投資家は、誰よりもこのルール変更を気に入ると言えるのだろうか。それは小型企業がもつ財務構造に理由がある。一般的に小型企業は、大企業と比べて内部留保が乏しく、外部資金、つまり借入金に頼る傾向が強い。つまり、負債比率が高く、利子の支払いが多いため、追加の税控除によって得られる利益のインパクトが大きい。(負債比率が高いため、金利上昇時はアンダーパフォームしやすいといえる)
さらに、小型企業は成長段階にあり、設備投資やソフトウェア導入などに積極的なケースが多いため、小型企業の減価償却費は、大型企業と比べ相対的に大きいことも味噌である。小型企業のEBITDAはEBITよりもはるかに大きく、税控除の分母が大きくなるため、より多くの利息費用を税額控除の対象とすることができる。
ラッセル2000:米国の小型株指数ラッセル2000で、今回のルール変更による影響をみてみる。バークレイズとバロンズによれば、2024年のEBITは約870億ドルだったのに対し、減価償却費は1090億ドルに上る。両者を足すと、EBITDAは1,960億ドルとなる。新ルールの適用によって、利子控除の計算対象(分母)が実に2倍以上に膨らむことになる。控除の幅が広がれば、それだけ課税所得が圧縮され、最終的な税負担が軽くなる。
このようにして企業に残るキャッシュフローが増えれば、その資金はさらなる設備投資、研究開発、人材獲得、あるいは配当・自社株買いといった株主還元に充てることが可能となる。結果として、企業価値が高まり、株価の上昇が期待できる。これが、米国の小型株投資家がトランプ大統領の『ひとつの大きくて美しい法案』を、どの投資家よりも気に入るだろうと考える背景である。

